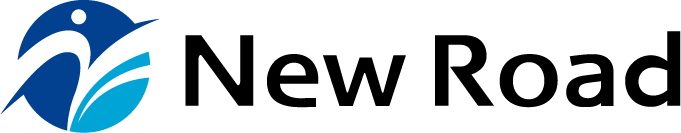東京2020大会では、多くの日本人選手の活躍が日本中を沸かせた。しかし一方、トランスジェンダーや宗教、国籍、紛争など、さまざまな国際・平等問題が可視化された大会でもあったと言えるだろう。閉幕した今、果たして東京2020大会はスポーツ・競技を通じて、多様性やインクルージョンを取り入れたスポーツ界を実現できたのか。これについて、先日開催された一般社団法人SDGs in Sports主催のオンラインイベント『多様性と調和の視点から見るBEYOND東京2020』から考えてみよう。
東京2020大会では、多くの日本人選手の活躍が日本中を沸かせた。しかし一方、トランスジェンダーや宗教、国籍、紛争など、さまざまな国際・平等問題が可視化された大会でもあったと言えるだろう。閉幕した今、果たして東京2020大会はスポーツ・競技を通じて、多様性やインクルージョンを取り入れたスポーツ界を実現できたのか。これについて、先日開催された一般社団法人SDGs in Sports主催のオンラインイベント『多様性と調和の視点から見るBEYOND東京2020』から考えてみよう。
目次
イベント概要

<主催協会について>
一般社団法人SDGs in Sportsはアスリートや関係者、有識者、一般の方と多岐にわたる分野の方と勉強会などを通じてスポーツ界を盛り上げること、そしてアスリートのリーダーシップやオーナーシップを高めていくことを目的に活動している。
<司会進行>
生島淳さん(スポーツジャーナリスト)、井本直歩子さん(アトランタ五輪競泳選手)
<パネリスト>
・「障がい者・パラリンピックの課題」大日方邦子さん
アルペンスキー・パラリンピアン、日本パラスポーツ協会*理事、日本パラリンピアンズ協会会長
*2021年10月1日、日本障がい者スポーツ協会から名称変更
・「ジェンダーの課題」杉山文野さん
元フェンシング日本代表、日本フェンシング協会理事、東京レインボーパレード共同代表理事
・「男女平等の課題」來田享子さん
中京大学 スポーツ科学部 教授、日本スポーツとジェンダー学会会長、東京2020組織委員会理事
多様性とインクルージョンの定義
まず、ここで語られる多様性・調和・包括について確認しておこう。イベントでは、冒頭で以下のように定義づけされた。
ダイバーシティは「多様性」「一人ひとりのちがい」、インクルージョンは「包括・包含」「受け入れる・活かす」という意味を持ちます。多様性は、年齢、人種や国籍、心身機能、性別、性的指向、性自認、宗教・信条や価値観だけでなく、キャリアや経験、働き方、企業文化、ライフスタイルなど多岐に渡ります。多様な人々が互いに影響し合い、異なる価値観や能力を活かし合うからこそイノベーションを生み出し、価値創造につなげることができます。「ちがいを知り、ちがいを示す」、つまり、互いに理解し、多様性を尊重するからこそ、個々の人材が力を発揮できる社会を目指します。
(イベント当日の配布資料より抜粋)
生島さんから、ラグビー日本代表ヘッドコーチを務めたエディ・ジョーンズの多様性(ダイバーシティ)とインクルージョンについて、印象的なエピソードが語られた。
「集団というものは色々な社会経験をしてきた人で構成した方が、総和の力やレジリエンス(自己に不利益な状況を乗りこえる力)が大きくなる。エディ氏は海外からの選手も多いチームにおいて、食事の際は特定の選手で固まらず、選手同士がより多くのコミュニケーションを図れるように、誰がどのテーブルに座っているかにまで気を配っていた。多様性を日常から確保していくことが強さにつながる」。
このエディ氏の教えは、今回のテーマにおける一つの答えを示唆する内容と言えるだろう。
LGBTQについて法整備の進まない日本と、東京2020大会でのカミングアウト

東京2020大会で高飛び込みの金メダリストに輝いたトーマス・デイリー氏の「今、金メダリストになって誇りを持って言うことができる。私はゲイで五輪チャンピオン。」という言葉は、印象的なものだった。東京2020大会のLGBTQについて、杉山さんからの報告内容をご紹介しよう。
「東京2020大会でLGBTQをカミングアウトした選手は、五輪だけでも180人以上(パラを含めると200名以上)。2012年ロンドン五輪は23人、2016年リオ五輪では56人だったのに比べると、時代の後押しとともにカミングアウトするアスリートが増えました。カミングアウトは必ずしもする必要はないと思っていますが、“言わないこと”で心理的安全性が保てない部分もあります。一方、カミングアウトによって関係者やファンを失望させてしまうのではないかと、不安を抱いているアスリートもいて実際に相談を受けたこともあります。今回、日本人選手でのカミングアウトは0人でした。カミングアウトするアスリートが多い国は法整備が進んでいる国です。アジア全体では少ない傾向にあり、日本は開催国であるにも関わらず、オリンピック憲章にある性別及び性的指向による差別の禁止が保障されていません。法整備がまったく進んでいないまま開催に至ってしまったという、日本の現状が明らかになりました。」
杉山さんからのデータ提示・考察によると、GBTQの当事者である選手は競技へのプレッシャーとは別に、カミングアウトしないことによる心理的安全性が保てないという課題が照らし出だされた。しかし、たとえカミングアウトしても関係者やファン、あるいはSNSによる誹謗中傷を危惧する面もあるだろう。その解決の鍵は個人の姿勢ではなく、国家の姿勢ではないだろうか。OECD(経済協力開発機構)が発表したLGBTQに関する法整備によると、日本は35カ国中ワースト2位というデータがある。前回のリオ五輪よりカミングアウトする選手が増加したにも関わらず、日本では一人もいないという現実。オリンピック憲章が求める「差別を受けることなく権利や自由が享受できる」には、不相応であったと言わざるを得ない。
・参考:THE FORUM NETWORK「Beyond the Rainbow: Achieve LGBTI + Equality」
東京2020大会は障がい者の多様性・インクルージョン実現に向けたスタート地点

障がい者のインクルージョンについては、大日方さんから次のように述べられた。
「東京2020大会では、多くの日本人がパラリンピックを目にしました。時差がなく、自宅待機期間も要因だったかもしれません。これまでパラリンピックという言葉は知っていても実際は見たことがないという時代が続きましたが、それを変えたかもしれません。多様性・インクルージョンが可視化されたことで、実現していくことはこれからの課題であり、ここからスタートするという意味でも意義ある大会だったとしたいです。課題としては、心に中にある意識をどう行動に変化させていくのか。一方で、社会の仕組みで分けないことと、“みんな”の輪をどのように広げていくのか。これを継続的に続けていくことが課題かと。」
生島さんの指摘によれば、ここでの“分ける”とは、例えばオリンピックとパラリンピックの選手が同じ環境・場所で練習をできるようにしていくこと。現状は分けられていることが多いようだ。
東京2020パラリンピックでは金メダル13個(リオパラリンピックでは0個)という快挙の後押しもあり、パラリンピック後、スポーツ庁が「障害者スポーツプロジェクト」を立ち上げたことが発表された。以前は障がい者スポーツを普及しようにも施設がない、整備されていないなど、さまざまな問題が障壁となっていた。そこへ、やっと国がバックアップする体勢に入ったのだ。しかし共生社会の創造に一役買うとはいえ、正直「今更」と思う節は拭えない。それでも、実現に向けた大きな一歩を踏み出した東京2020パラリンピックのレガシーであると考えたい。
二軸ではなく“多軸”で考えることの重要性
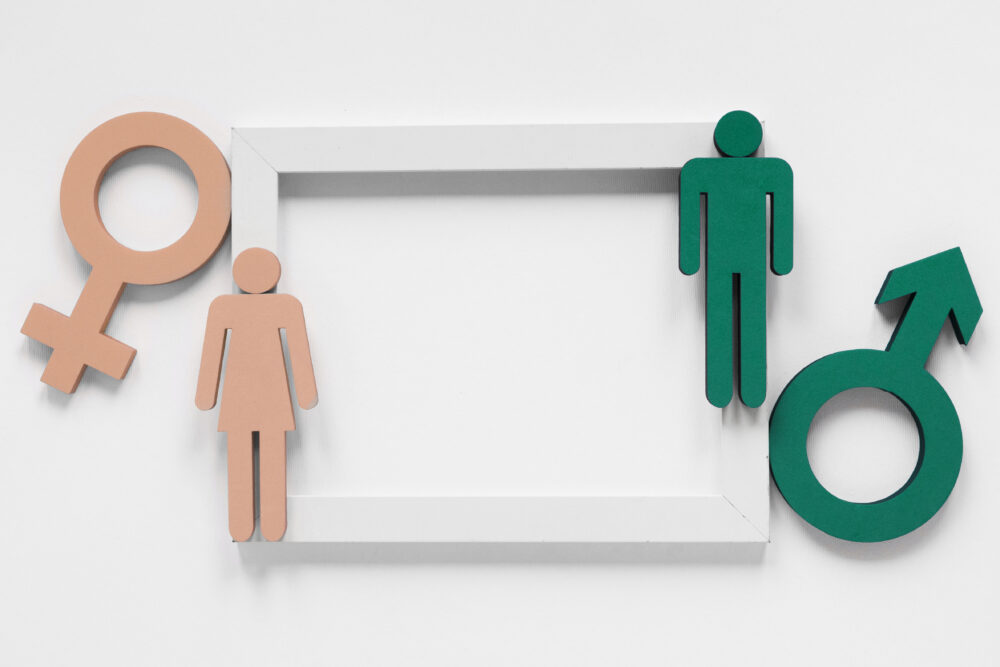
ジェンダー平等の問題点は、2月3日に開催されたJOC評議員会において当時の東京オリンピック・パラリンピック大会組織委員会の森喜朗会長の女性差別発言を前提に、この問題を契機とし、実際に組織委員会の中でどのような働きが行われたのかを來田さんが伝えてくれた。
「2021年2月の森氏の発言は、私たちには忘れられない、忘れてはいけない日となりました。そのような意味で、東京2020大会はエポックメイキング(画期的)になったかと。スポーツ庁がまとめた中央競技団体の運営指針「ガバナンスコード」では、女性理事の割合で40%以上の目標を掲げました。では、なぜ40%という数字が出てきたのかというと、2014年にWHOが統計で出した世界でスポーツの活動にアクセスできている割合が約40%。五輪の女性参加割合も40%を超えたくらいで、この数字は母集団を反映し、参加している人が声を出せる状況を反映させようと出された数字です。社会集団に関する研究において、マイノリティの人が集団の中で30%を超えると、無視できない臨界点を超えるとされています。40%という数字を理解し、今後どう活かされるのかが課題です。森氏の発言後、組織委員会に追加された女性理事たちは活発に発言するため、会議は長くなりました。その点は、確かに森氏の意見が正しかったですね。しかし、民主主義と多様性と調和を模索する道は、ときに手間がかかるものです。お互いに意見を削減することのデメリットの大きさを認識することの変化があったのかと思います。」
各パネラーの活動内容と課題の報告を踏まえ、生島さんは多様性とインクルージョンに関して「(東京2020大会で)やっと土壌が耕され始めたところ」と定義づけた。そのうえで、大日方さんから提示されたのが「多軸で考えることの重要性」というキーワードだ。
日本では以前まで、「健常者・障がい者」「男・女」のように二軸で語られることが多かった。しかし、例えば大日方さんは「障がい者であり女」であるように、二軸では語れない部分を指して「議論の中で、多軸でどう話し合っていけるのか。結論としては『どっちでもいい』という答えにならないといけない」と話す。さらに來田さんは、次のように二軸論で生じる問題点について触れている。
「今回、オリンピック・パラリンピック開催の是非に当たり二軸で話が展開していき、私たちが社会に求めるビジョンは何なのかという議論の場を失わせてしまいました。では、その軸をどうやって増やすのかについては、オリンピック憲章のさまざまな差別のカテゴリーに敏感になっていかなくてはいけません。そうした色んな人の立場を考えながらイメージする力を、日本の教育の場で育てていかなくてはいけないのです。」
これについて生島さんは、スポーツ報道する立場から、「メディアは勝ち・負けのように二軸論の文法が対立を描きやすい。日本は他国と比べても二軸論に慣れているのでそれを変えていく必要がある。」と分析した。
こうした課題・問題点が列挙される中、では現実的に多様性・インクルージョンをどう実現していけば良いのか。このテーマに対し、杉山さんが例えを挙げて次のように述べている。
「公園のシーソーに例えると、両端にそれぞれ重たい人(強者)と軽い人(弱者)がのって傾いたシーソーを真ん中(平等)にしたい場合、あなたはどこに乗りますか?中立な立場なのでと真ん中に乗ってしまう人が多いのですが、しかしシーソーを平行にしたい場合(差別がない状況)は真ん中に立つのではなく、軽い方に寄り添わなくては平行にはなりません。マイノリティは多数決で解決はできません。真ん中にしたいのか、それとも真ん中でいたいのか。このことを、今一度考える必要があります。そして多様性の実現は、一人の反対する声の中にヒントがある。向き合い、時間をかけて、無駄に思うような議論でも、一度問題点をすべて出してとことん話し合う。多様性と効率は相性が悪く、今までの効率重視の方法では小さな声は届きませんでした。一つの答えではなく、多数の答えがあっても良いのではないかと思います。」
オリンピックとパラリンピックを東京で開催したことによる最大のレガシーは、開催の可否や政治問題、平等についてなど、さまざまな社会的な課題・現状が浮き彫りになったことかもしれない。日本において、これらの問題は当事者の課題・問題として語られることが多い。しかし、世界的なスポーツの祭典で可視化されたことは、国民の意識に大きな影響を与えたと言えるだろう。
「みんな一緒、そしてみんな違う」の理解へ
多様性と調和の実現には、効率を求めがちな世の中とは相反する「時間がかかる」「やり尽くす」ことが必要という言葉が印象的だった。マイノリティの経験を持つ人たちは、この言葉を深く受け止めているのかもしれない。しかし、今回キーワードとなった「多軸で思考できる社会構造をいかに創っていけるのか」という点が、今後の課題なのではないかと感じる。東京2020大会はスタートライン。実のところ日本はそのスタートラインにすら立っていなかったのだという気づきを、閉幕した今になって得た。
[著者プロフィール]
 |
たかはし 藍(たかはし あい) |

スポーツメディア「New Road」編集部
読者の皆さまの心を揺さぶる、スポーツのさまざまな情報を発信しています!